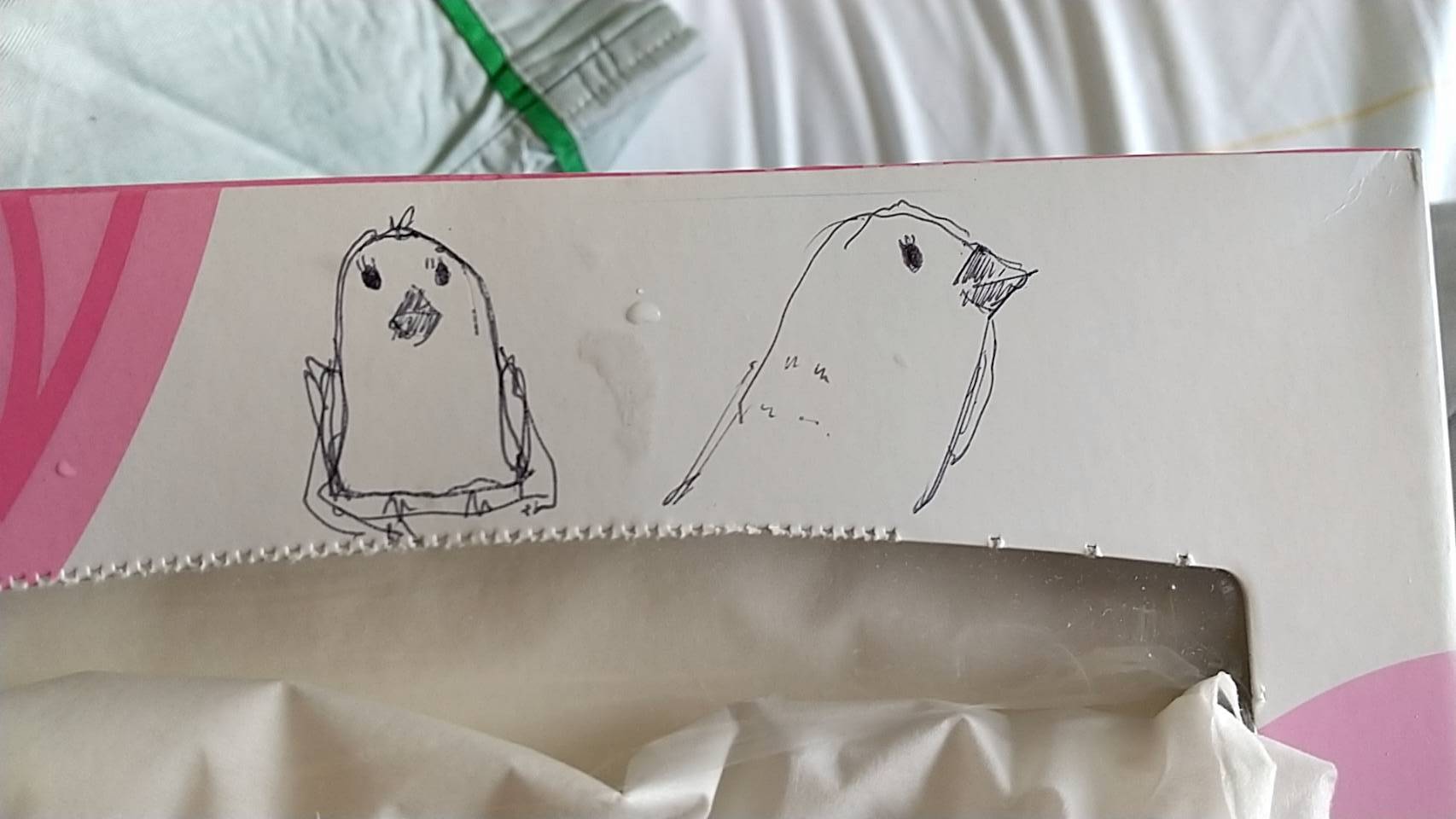7月8日木曜日、上顎洞がんの手術を行いました。
上顎洞というところはとても複雑な形をしていて、手術には時間と技術を要します。眼球、骨、上顎と複雑に入り組んだ組織に、どのようなアプローチをするのか――まるで医療ドラマさながらの緊迫感ある説明が行われました。
その説明が佳境にさしかかったところで、ドクターは言いました。
「取っただけだと空洞になってしまうので、そこにお腹の肉を持ってきて、かぽっと埋めます」
……突然、アナログ的に「かぽっと」お腹の肉が入ります。
しかも、お腹の肉にも「良い状態」というのがあるそうで、厚すぎてもいけないし、薄すぎてもいけない。
食べること飲むことが大好きな私のお腹の肉は当然、厚いわけで……調べた結果、こう言われました。
「この1か月で5キロの減量を目指しましょう」
簡単ではありませんが、1か月で5キロならなんとかなるかと、たかをくくっていました。
――その話し合いの3日後。
「手術の空きができたので、今週手術しませんか」
「お腹が出ているまんまですが……」
「できないことはありません」
「……」
というわけで、私は私にとって緊急となる手術を受けることになりました。
普通、手術を控えて不安になるとしたら――
「腫瘍の切除は成功するか」「どんな後遺症が残るか」といったことだと思います。
でも私の場合、
「軽肥満の腹が顔に“かぽっ”とはまることで、一体どんな顔になるんだろうか」
というのが、最大の関心事でした。
結果、10時間以上におよぶ大きな手術となりました。
私は寝ていただけなので、手術中に――
医局の中の出世をめぐるドロドロの人間模様が露出してしまったり、
ナースのひとりが、思いを遂げられない若いドクターの背中に胸を締めつけられて手術室を飛び出していったり……
そんなドラマが繰り広げられていたかどうかは、うかがい知ることはできません。
ともかく、手術は無事に終了。
私は手術室からHCU(高度治療室)へと運ばれました。
そのとき――
「いや~~~~!!!」
「ああ~~~~!!!」
「いや~~~~!!!」
「いや~~~~~~!!!」
悲痛な叫び声が、大きく響き渡ったのです。
現在、新型コロナによる感染予防のため、手術前後に患者と家族が接触することができません。
家族は、ストレッチャーで運ばれていく患者をほんの一瞬、通路からちらっと見るだけ。
手を握って声をかけたり、終わった後に「がんばったね」と言うこともできません。
私は、そうした状況もあって、「なんの心配もないから、家で待っていて」とパートナーに伝えていたのです。
でもたまたま、その叫び声の主と関係のある患者さんと、私のタイミングが重なったのでしょう。
私は、まだはっきりと意識のある中で、その地獄のような悲鳴を聞くことになったのです。
時間にして1分程度――
きっと、あの声は家族。
息子か娘か、父か母か、大切な人に違いありません。
あらん限りの声で、何度も何度も叫び続けていたのですから……。
でもね、見ればわかると思うんです。
ストレッチャーの上には、ぐったりした私もいたわけで。
あんな悲鳴を聞かされたら、さすがに不安になります。
「失敗しない女医さん」のドラマをはじめ、多くの医療ドラマでは、
執刀医が興奮気味にスタッフと会話を交わし、活気あふれる中で患者とともに治療室へ向かう――
そんな光景はあまり描かれません。
私が言いたいのは――
そこは明らかに“公共の場所”だということなんです。
だから、できれば大声を出すのではなく、不安げな表情でギュッと拳を握るくらいにとどめていただけないか、と。
……いや、手術が終わって3日目で体がきついからといって、
こんなふうに人を責めるようなことを書くのはよくないですね。
私の顔は、軽肥満のお腹の肉が「かぽっ」とはまり、見事な満月状態になっています。
まだ腫れていて、そう見えているだけかもしれませんが……
今後どうなるかは、また追ってご報告いたします。